広告
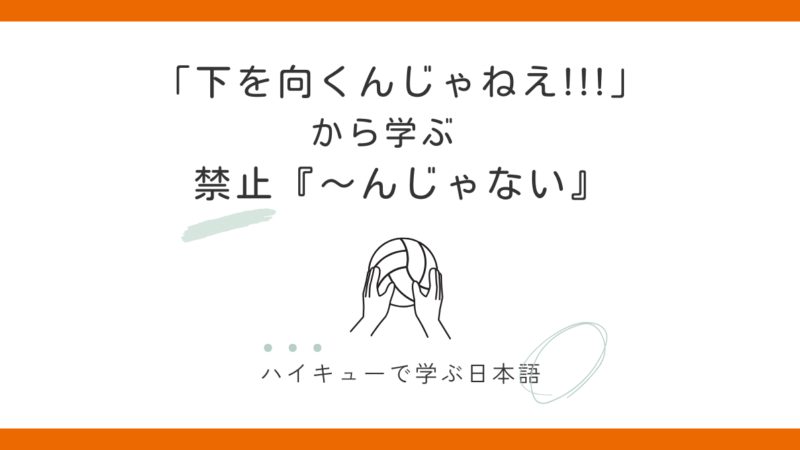
オンライン日本語教師のちゃそです🏐
大好きな『ハイキュー!!』のセリフから日本語の表現を学ぶシリーズです!
今回は禁止表現「〜んじゃない」を取り上げます。
この記事では、「んじゃない」の意味と使い方を説明しながら、実際にマンガ『ハイキュー!!』の中で、どのように使われているのかを見ていきます!
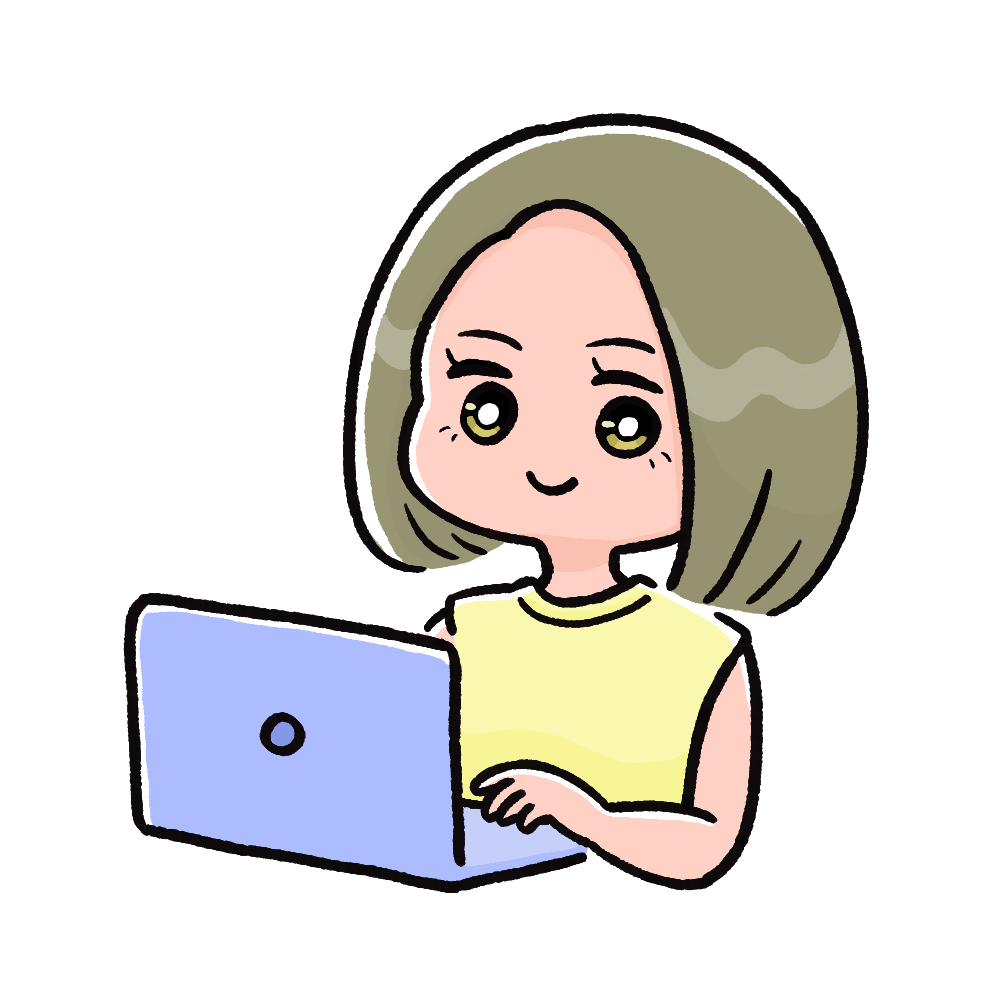
春高予選の決勝戦!烏野VS白鳥沢戦のマッチポイントから✨
Amazonプライム会員なら、Amazonプライムビデオでハイキュー!!が全話無料!
>>Amazonプライム会員「30日間の無料体験」はこちら
ハイキューで学ぶ「V-るじゃない」
では、実際のマンガの場面を見てみましょう!
引用:『ハイキュー!!』第21巻 第183話 欲しがった男(古舘春一/集英社)
烏養コーチ:「下を向くんじゃねえええええ!!! バレーは常に上を向くスポーツだ」
春高予選、宮城県大会決勝戦。白鳥沢学園のマッチポイント。
春高常連校である白鳥沢の押せ押せムードで、会場全体が「あと1点」コールに包まれています。
体力も精神も限界に近い烏野の選手たち。
重い空気に飲まれそうになったその瞬間、烏養コーチが放ったのがこの言葉でした。

見るたび、泣いちゃう(´;ω;`)熱いセリフ…🔥
文法解説:「V-る んじゃない」の基本
「〜んじゃない」は、”それをするな!”という禁止を表す言葉です。
- 接続:動詞辞書形 + んじゃない(のではない)
- 意味:禁止・注意
- 使用:話し言葉。親しい間柄や、目上の人が下の人に使う。
- 男性:「〜んじゃない」「〜んじゃねぇ」(さらに砕けた形)
女性:「〜んじゃありません」という丁寧形を使うことが多い
この「~んじゃない」は下降調のイントネーション(↘)で発音されます。
※上昇調「〜んじゃない?↗」は「〜じゃないの?」という確認などの意味になる、別の表現です。
例文もみてみましょう
- そんなところで遊ぶんじゃない
- 電車の中で走るんじゃない!
- そんな小さい子を突き飛ばすんじゃない!
- 無理するんじゃないよ。体が一番大事なんだから。
- 諦めるんじゃねえ!まだ終わってない!
禁止「V-る んじゃない」の特徴
「〜んじゃない」には、おなじ禁止表現の「〜な」にはない特徴があります。
それは、聞き手がすでに知っていることを、強調して伝えるという点です。
具体的に見てみましょう。
状況:ダメだと知っているのに、やろうとしている
「〜んじゃない」が使われるのは、こんな状況です
- 聞き手は「それはダメだ」ということをすでに知っている
- でも今まさに、その行為をしている/しようとしている
- だから話し手は「わかってるよね?」と強調して止める
例:そんな小さい子を突き飛ばすんじゃない!

もし子どもが自分より小さい子を突き飛ばしていたら
大人が「そんな小さい子を突き飛ばすんじゃない!」と言いますよね。
この状況は
- 「小さい子に乱暴しちゃダメ」ということをすでに知っている
- でも、やっている/やろうとしている
- 知っているはず(だろう)のことを強調して止める
怒られた子は、「小さい子に乱暴しちゃダメ」ということはすでに知っています。
(例えば以前にも怒られたことがある、小さい子は自分より弱いって理解しているはず など)
でも今まさに、突き飛ばした/突き飛ばそうとしている状況です。
だから「突き飛ばすんじゃない!」と、知っているはずのことを強調して止めています。
もし「突き飛ばすな!」だけなら、単なる命令です。
でも「突き飛ばすんじゃない!」だと、「ダメだってわかってるでしょ!?」というニュアンスが含まれます。
望ましい行為を提示
「〜んじゃない」で望ましくない行為を止めたあと、よく望ましい行為が提示されます。
(言わない場合もあります)
例)電車の中で走るんじゃない。人にぶつかって危ないだろう。静かに座ってなさい。
- 望ましくない行為: 電車の中で走る
- 理由: 人にぶつかって危ない
- 望ましい行為: 静かに座る
このように、「〜んじゃない」のあとには、「こうしなさい」と望ましい行為が続くことが多いです。

相手がダメだとわかっているはずのことを強調して「ダメだ」と禁止してるんだね
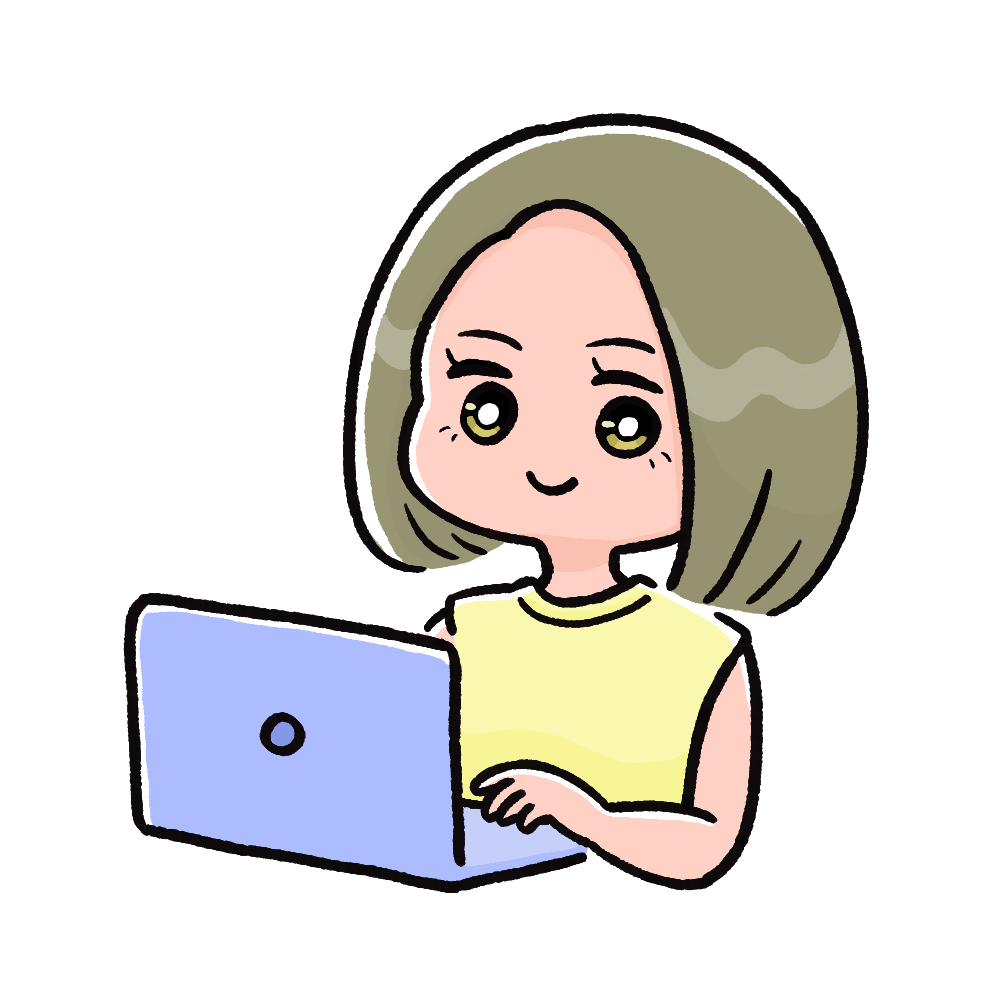
その後に、やるべきことも伝えることが多いです

だから親が子どもを叱るような状況でよく使うんだね!
ハイキューで読む「下を向くんじゃねえ」の背景
では、烏養コーチのセリフに戻りましょう!
引用:『ハイキュー!!』第21巻 第183話 欲しがった男(古舘春一/集英社)
状況は
- 白鳥沢のマッチポイント(相手があと1点で勝ち)
- 会場は白鳥沢寄りの応援の雰囲気
- 選手は体力も精神も限界
- 目線も気持ちも、下を向きそうになっている

こんな状況なら、誰だって下を向いてしまいそうになるよね💦
「下を向くな」と「下を向くんじゃねえ」|禁止形との違い
もし烏養コーチが「下を向くな!勝つぞ!」とだけ言っていたら…?
これは単なる命令ですよね。
→ 烏養さんの戦術的な指示・命令になります。

禁止の命令表現だね
でも「下を向くんじゃねぇ」だとどうでしょうか?
→ 選手たちがすでに知っていることを、強く思い出させる表現になります。
選手たちが知っていること
烏野の選手たちは、この状況で下を向いてしまったら負けることをわかっています。
気持ちも姿勢も下を向いてしまったら、試合に勝てない。
これは、バレーをやっている人なら知っていることですよね。

こんな状況で気力を保っていられるのも、才能だよね!
烏養コーチが伝えたこと
選手たちは最初「負けるから下を向くな」「勝ちたいなら下を向くな」と思ったかもしれません。
でも、烏養コーチが伝えたのは、それじゃありませんでした。
「バレーは!!!常に上を向くスポーツだ」
これを、『望ましい行為』のとして提示したのです。
バレーの本質である
- バレーは常に上を向くスポーツである
- これがバレーの本質だ
- だから、どんな状況でも下を向くべきじゃない
という、バレー選手としての在り方の話をしたのです。
勝ち負けを超えた、バレーの本質の話を再認識させた、思い出させたんだと思います。
だからこそ、選手たちの心に深く刺さる言葉になったのだと思います!

烏養コーチが語ったのは、根性論でも応援でもなく、バレーの本質だったわけだ!

この後の烏野メンバーの表情を見たら、しっかり伝わったことが納得できるね!
引用:『ハイキュー!!』第21巻 第183話 欲しがった男(古舘春一/集英社)
まとめ:「~んじゃねえ!」から読み取るコーチの思い
「V-る+んじゃない」をハイキューのシーンから読み解きました。
「下を向くんじゃねぇ」という烏養コーチの言葉選び。
単なる「下を向くな」という禁止ではなく
- 選手たちに、すでに知っている「バレーの本質」を思い出させる
- 苦しい場面だからこそバレーの本質が深く響く
表現の使い方が、このセリフをより深く、より心に響くものにしているんですね。

ただの叱咤激励じゃない。バレーの本質を思い出させる言葉だったんだね!
このセリフは、烏養コーチ役の声優・田中一成さんが生前に収録した最後のセリフでもあります。
次の話から声優が交代したこともあり、ファンにとっても特別な意味を持つシーンですよね(´;ω;`)
文法の深さと、このエピソードが重なって、より一層心に残る言葉となっています。
烏養繋心役を演じてくださいました田中一成さんのご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。謹んでご冥福をお祈りいたします。 pic.twitter.com/R9xVBPclR8
— ハイキュー!!.com (@haikyu_com) October 14, 2016
文法のルールだけではなく、感情と一緒にことばを読むことで、表現の深さがもっと見えてくる――
この記事がそんなきっかけになればうれしいです!
最後まで読んでくれてありがとうございます!
感想やお気に入りのシーンがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね!
この記事を書くために使ったもの紹介
引用元について
本記事で使用している画像・セリフは著作権法第32条に基づき、教育・批評を目的として引用しています。
- 作品名:『ハイキュー!!』
- 著者:古舘春一
- 出版社:集英社
- 引用巻数・話数:第21巻 第183話 欲しがった男




