広告


動詞のグループ分けがわかりません。
国語で習った「五段活用」とかが関係しているみたいだけど・・・
学習者に聞かれてもどう説明すればいいかわかりません。
おしえてください。
こんな疑問にお答えします
この記事の内容
- 【瞬時にできる】動詞のグループ分け
- グループ分けの教え方のポイントとコツ(ます形・辞書形から)
この記事の信頼性
- 2012年日本語教師養成講座420時間修了
- 日本語教育能力検定試験 合格
- 2019年~現役オンライン日本語教師
この記事を読めば、動詞のグループ分けをマスターできます!
検定試験対策本のグループ分けの説明は少し複雑ですよね。
教師も、学習者と同じシンプルな分け方を理解すればOKです。
日本語教育の動詞とは
まずは、日本語教育の動詞の扱い方についでです。
- 動詞を3つのグループに分ける
- 「五段活用」や「上二段活用」などの表現は使わない
- 動詞の数の多さは 1>2>3 グループの順
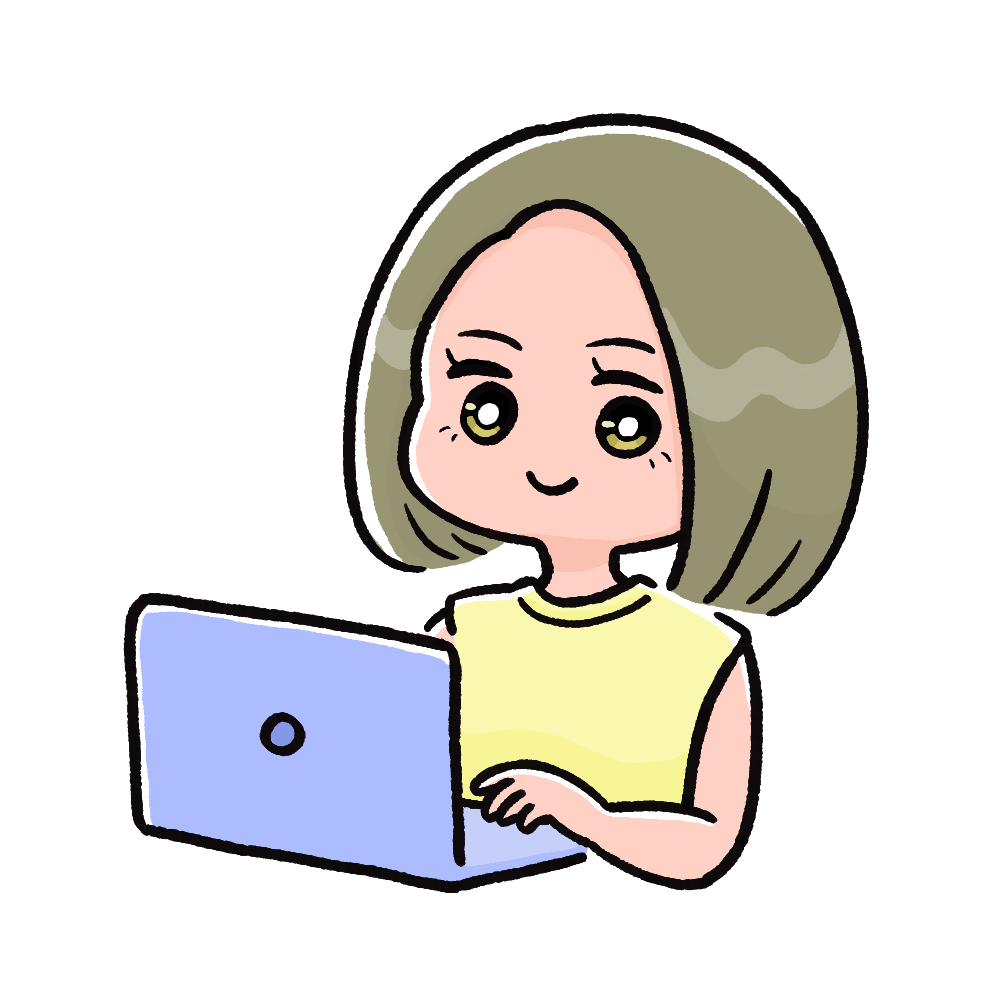
では、どうして動詞のグループ分けが必要なのでしょうか?
学習者は、こんな疑問を持っています

「着る」は「着ます」と言うのに、「切る」は「切ります」です。
どうして「切ます」じゃないの?

え?どうしてかな?切るは「五段活用」?着るは「上二段活用」かな?えっと、、
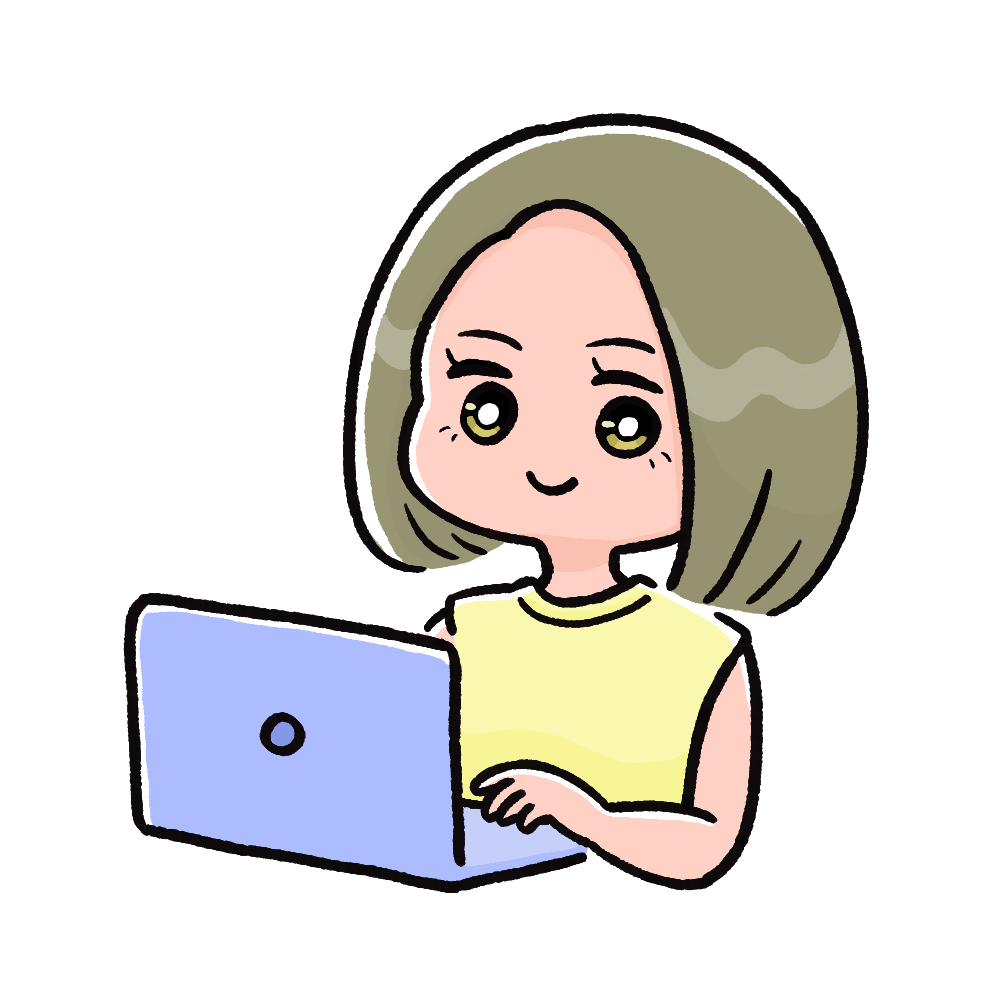
もっとシンプルに教えられる方法があるよ、ふふふ。
学習者が間違いやすいポイントでもあるので、ぜひ身に付けましょう!
動詞のグループ分けをマスターするだけで、授業に自信が持てますよ。
日本語教師が瞬時に動詞グループを見分けるコツ
教師は「ない形」から判断しましょう
- 「する」と「来る」⇒3グループ動詞
- 動詞を「ない形(~ない の形)」にする(ex 食べない 書かない)
- 「ない」の前の文字で見分ける
3グループ動詞は「する」と「来る」だけです。
3グループ以外は、「ない形」にして判断します
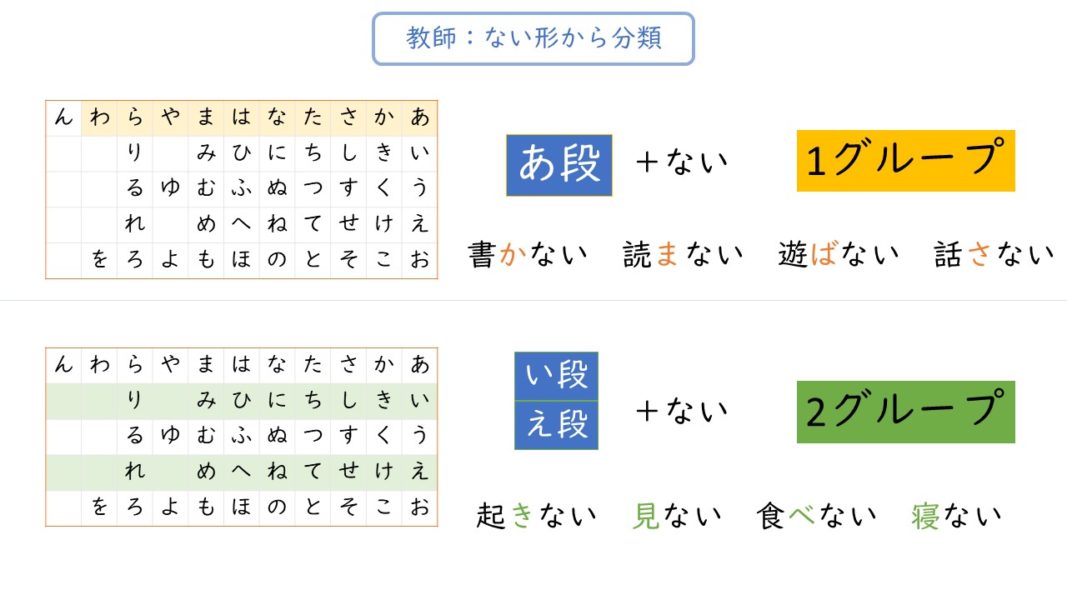
- 「あ段+ない」⇒ 1グループ
- 「い段+ない」or「え段+ない」⇒ 2グループ
「書く」⇒「書かない」⇒「あ段+ない」⇒ 1グループ
「食べる」⇒「食べない」⇒「え段+ない」⇒ 2グループ
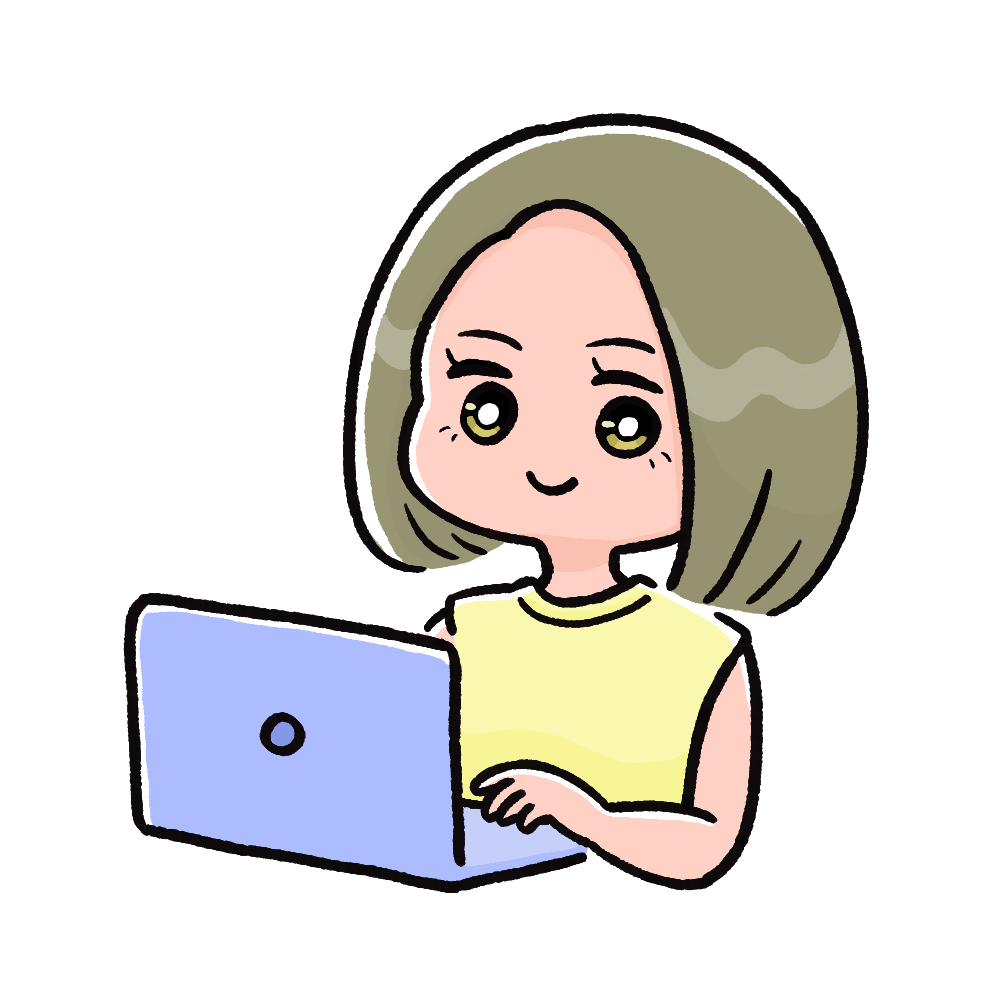
ない形の前が「あ段」なら1グループ。それ以外は2グループと覚えちゃいましょう!
動詞グループの見分け方:教え方のポイント
次は学生さんに教える方法です。
まず、教える前に確認しましょう!
- 3グループは「来る」と「する」の2つだけ!
- 50音表(あいうえお表)を用意する
- 「ます形」or「辞書形」どちらから見分けるかは、使用テキストによって違う
- 例外は一度に2~3個だけ提示する
まずは3グループは2つだけだから、覚えてね!と伝えましょう。
その後、1グループと2グループを見分けます。
「い段」や「え段」と口で言うより、50音表を見た方が早いです。
「ます形」か「辞書形」どちらから分類するかは、テキストによって違います。
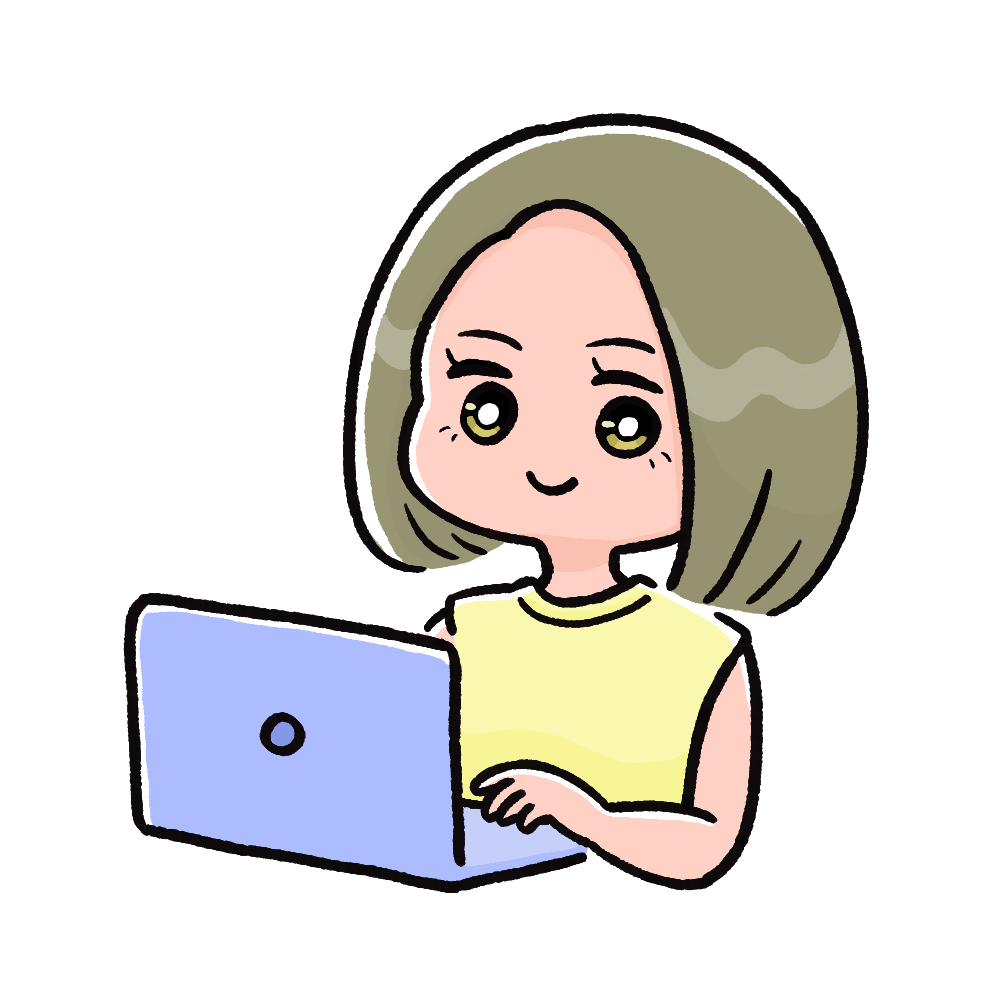
定番の「みんなの日本語」は、ます形から分類しています
それから、グループ分けの規則には例外もあります。
例外はたくさん提示すると混乱します。
一度に2~3個までにしましょう。
①ます形から分類:「ます」の前の文字は?
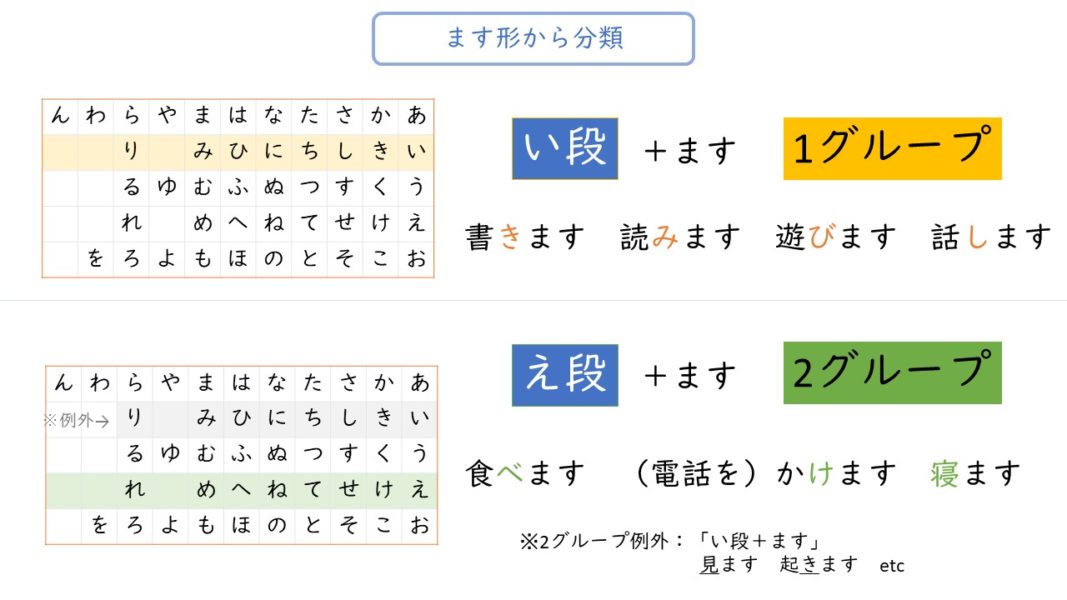
- 「い段+ます」⇒1グループ
- 「え段+ます」⇒2グループ(★例外:「い段+ます」)
「書きます」⇒「い段+ます」なので、1グループです。
「食べます」⇒「え段+ます」なので、2グループです。
1グループ⇒2グループ⇒2グループの例外 の順で教えるとわかりやすいです。
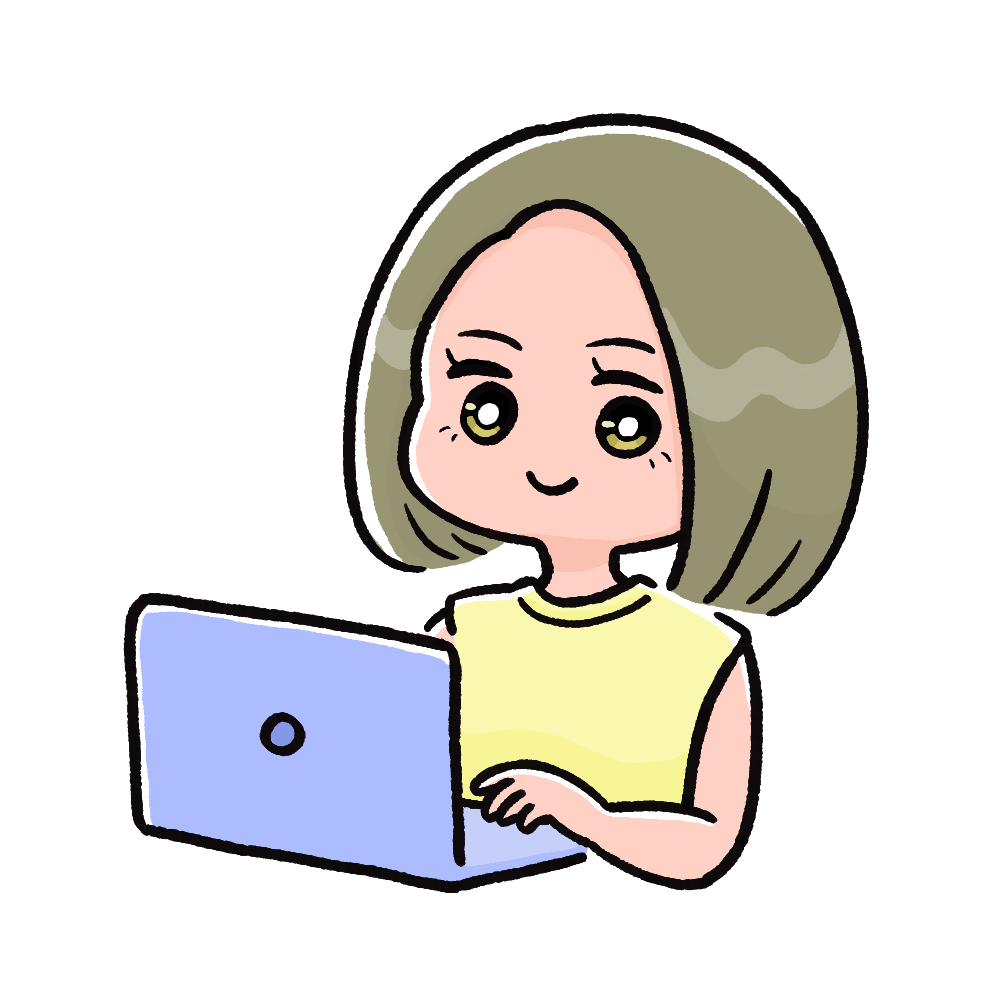
ルール通り⇒ルール通り⇒例外 の順ですね
②辞書形から分類(1):最後の文字に注目!
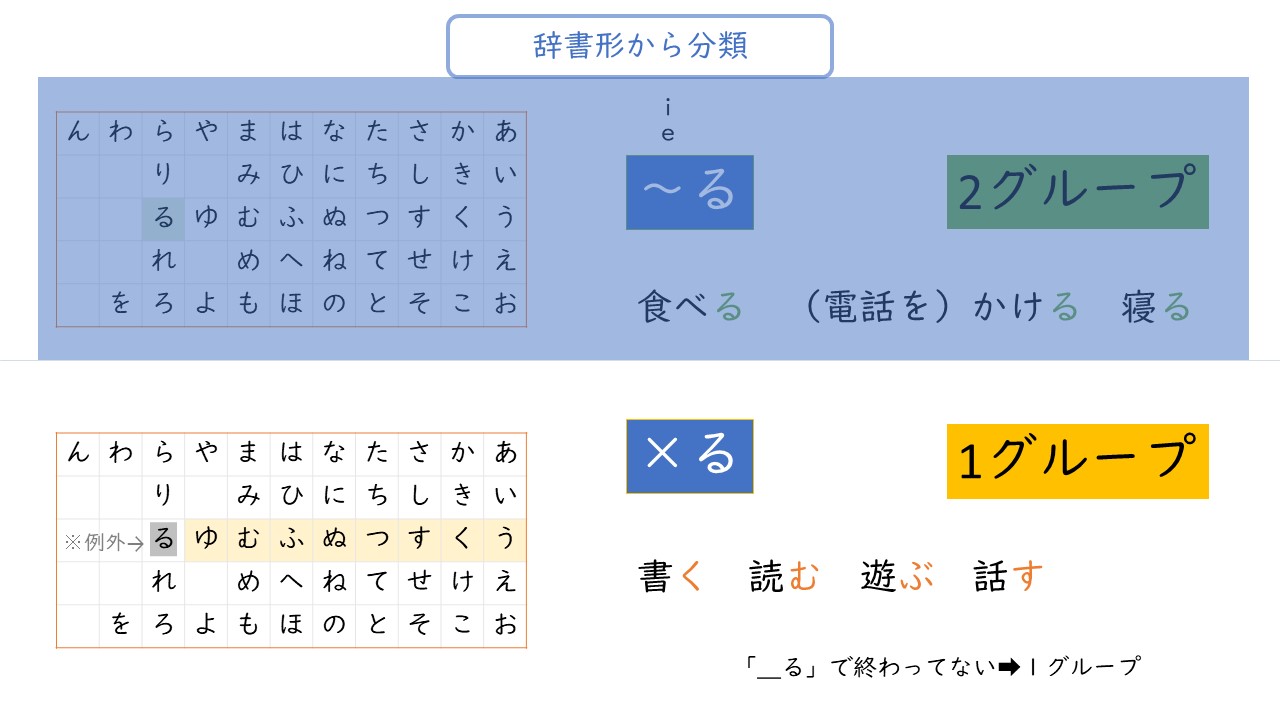
動詞が「る」で終わるかどうかで分類します。
- 「_る」以外で終わる⇒ 1グループ
「書く」⇒「く」で終わっているので、1グループですね。
「読む」⇒「む」で終わっているので、1グループですね。

「る」以外で終わる動詞は、1グループなんだね!
辞書形から分類(2):「_る」の見分け方
「_る」で終わる1グループもあります。
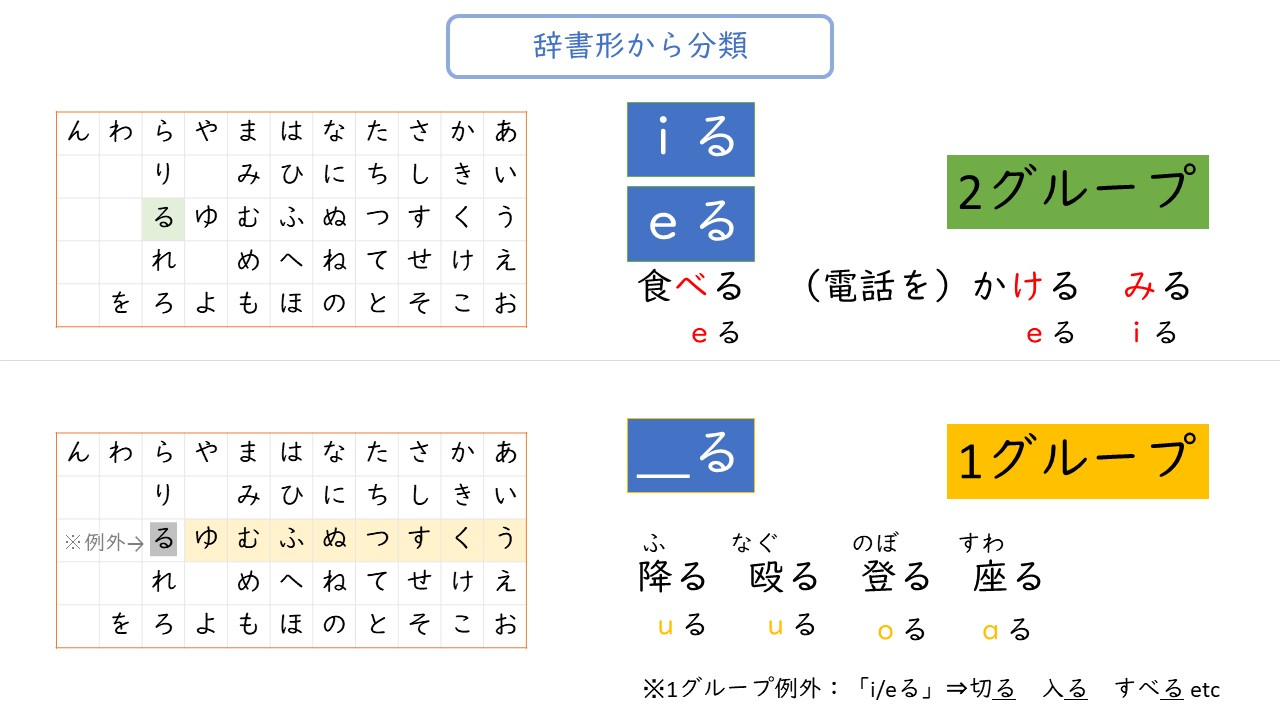
そんな時は、こう判断します。
- 「-iる」「-eる」で終わる ⇒ 2グループ
- 「-iる」「-eる」以外で終わる ⇒ 1グループ (※例外あり!!)
「-iる」と「-eる」について
★「-iる」か「-eる」で終わるのは2グループです。
★「-iる」か「-eる」以外の「_る」で終わる動詞は、1グループです。
でも、例外もあります。
「滑(すべ)る」は「-eる」ですが、1グループです。
「切(き)る」も「-iる」ですが、1グループなんです。

くう!!これが、噂の例外か・・・!
例外は悩ましいですよね。でも大丈夫です!
例外が出てきた時に、その都度、気をつけて覚えればいいんです!
まとめ:日本語教育の動詞のグループ分けは国語よりシンプル
- 動詞のグループは3つ
- 3グループは「する」と「来る」だけ!
- 動詞の多さは 1>2>3グループ
- ルール通り ⇒ 例外 の順で教える
- 学校の国語で習ったものは一度忘れてOK!
動詞のグループ分け、一人でできそうですか?
見分け方を知っているだけでも、授業に自信がもてます!
大切なのは、「学習者にどう伝えるか」です。
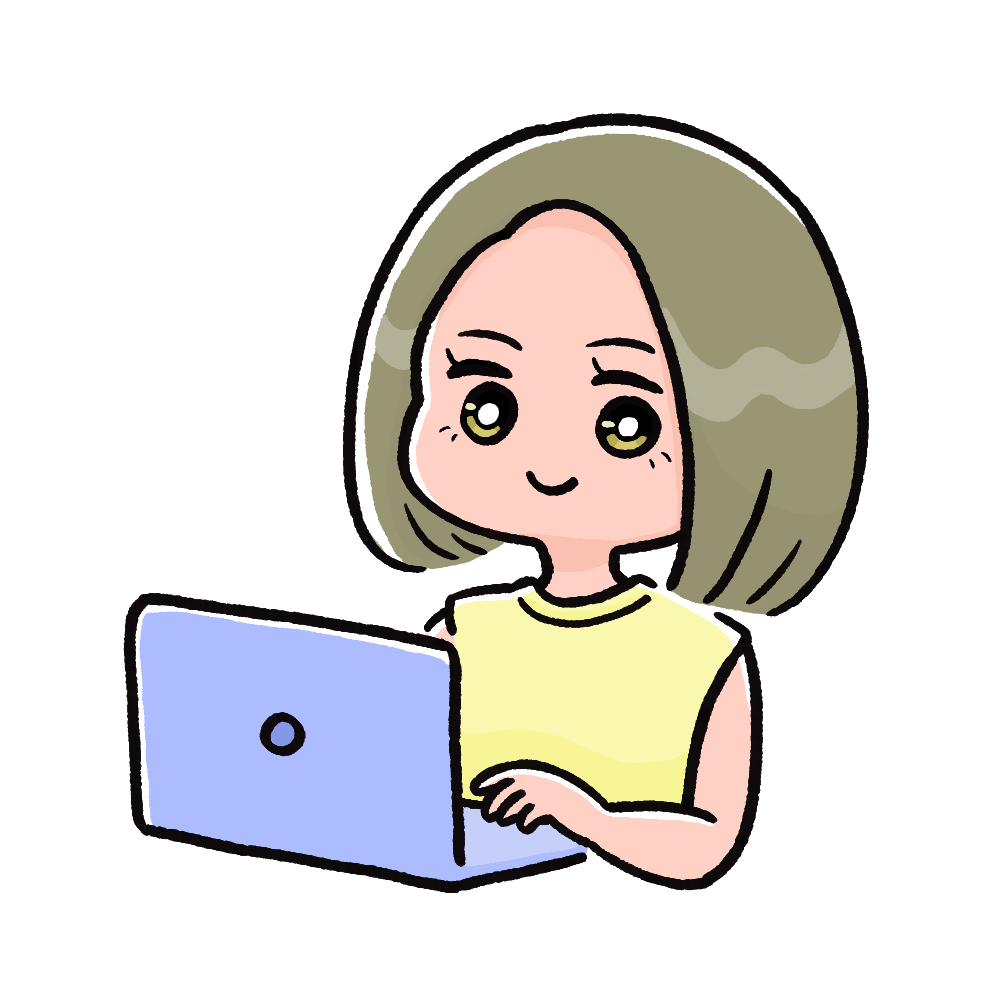
シンプルにわかりやすく理解してもらえるといいですね!
基本的な動詞の活用形についてはこちら↓
日本語教育を勉強したら、未経験でも働けるオンラインスクールがおすすめ!
コメント一覧
動詞が、そもそも1・2・3のどのグループに分類されるか、わからない生徒に、「【ない形】を考えたら、すぐわかるから良い方法だよ」って教えている先生がいる。その先生は、当コラムを見て、ひらめいたようだが、本末転倒だ。
Twitter でもツイートを参考にさせていただいています「台湾で日本語を教える毎日」の佐藤です。
わたしは長らく「ます形」からの動詞変化だけを教えて来たのですが、最近オンラインで教えるようになり、「辞書形」からの動詞の分類法を知りたいという学習者が現われ、教師自身もきちんと理解、整理できて、かつ学習者にも提示できる参考資料がないかを探していて、こちらに辿り着きました。
図表も非常にわかりやすく、参考にさせていただいたのですが、一点だけ気がついたことがあるので、こちらでお伝えします。
佐藤先生、こちらこそいつも参考にさせていただいてます!
ブログ読んでくださりありがとうございます^^
先生がお気づきになった点、ぜひ教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします
前回のコメントに続けて、「気がついたこと」も書いたつもりだったのですが、なぜか残っていなかったようで、失礼しました。(コメントの文字制限?)
「辞書形から分類(2):「_る」の見分け方」の図で、下の方に「1グループ例外」として「作る」が挙げられていますが、「作る」は、(Tsukuru)で、図が説明している「i/eる」の例外には当てはまらないのでは…。
わたしは、chasoさんの図表を参考にしながら、例外の代表例として、代わりに初級でよく出てくる「入る」(hairu)を挙げておこうかなと考えているところです。
うわああ~本当ですね!ありがとうございます!!!全く気づきませんでした(´;ω;`)
先生のアイデアをお借りして、「入る」に差し替えました。
本当にありがとうございます。


勉強になりました、ありがとうございます。
日本に来てからずっと日本語を勉強しましたが、未だによくわかりません。
これからも「ちゃそ」先生のblogを拝見しながら、日本語を勉強します。
また、よろしくお願いします。
ありがとうございます!^^すごくうれしいです!
私もまだまだ未熟なので、頑張って勉強していきます。
こちらこそ、よろしくお願いします